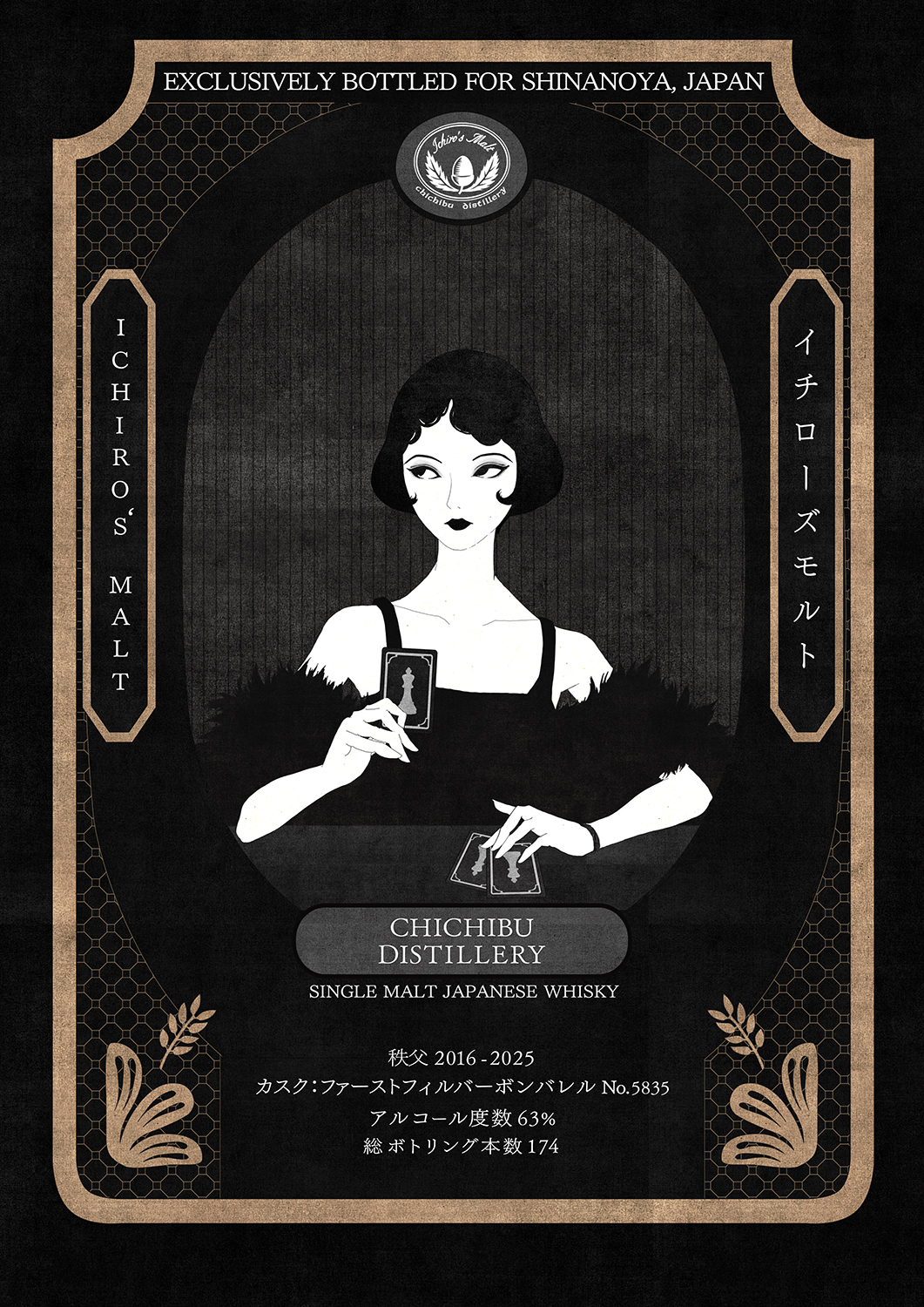変化するヴィンテージ:ワインの未来はどこへ?@cask 川上
目次
はじめに
こんにちは。虎ノ門caskでソムリエをしている川上です。
皆さん、ワインを開けた瞬間に「今年の出来はどんなかな?」とワクワクしたことはありませんか?
実はそのワクワクの裏には、ブドウ畑の成長に大きく関わる気候の変化というドラマがあるのです。
ワインはよく「テロワールの芸術」と呼ばれます。その土地の気候や土壌、人の知恵が一体となった結晶。つまり、1本のワインを味わうことは、その土地の物語を味わうことでもあります。
近年、地球温暖化の影響でテロワールが新しい表情を見せ始めました。これは大きな試練であると同時に、ワインの未来をもっと面白くするきっかけにもなっています。
ワインの苦悩:暑すぎる夏とブドウの変化
温暖化の影響もあり、積算温度も上昇しています。気温が上がると、ブドウはぐんぐん糖度を上げていきます。でも、上がり過ぎるとワインに爽やかさをもたらす酸が減っていってしまいます。
またブドウは、気温が35℃を超えると、ストレスで活動を止まってしまうこともあります。
それに対して生産者は知恵を絞ります。葉っぱで日傘を作るなど栽培方法を変えてみたり、ブドウの収穫タイミングを減酸する前に収穫したり、栽培する品種を変えてみたり、北向きの畑を開拓するなど今の環境に合わせて様々な対応しています。
またブドウの木も生きています。ある生産者はブドウの木が暑さに適応し始めているということを話す生産者もいます。環境に適応していく力がきっとブドウにもあるのです。
このように温暖化の中でも一年で一度しか生まれないおいしいワインが生み出されます。

産地の地図が広がるワクワク
これまで寒過ぎてワイン造りが難しかった場所、イギリスやスウェーデンなども新たなワイン産地として注目されており、オーストラリアでは、冷涼なタスマニア島にワイナリーが生まれています。
このように温暖化の影響で今までになかった新たな可能性を生み出しています。
注目のイギリスワイン
以前まではイギリスでブドウを栽培することは寒冷過ぎる気候のため、ブドウ栽培に適さない国でしたが、今では綺麗な酸味を残しつつ、品質の高いブドウが生産できるようになってきています。土壌もシャンパーニュに近い石灰質土壌から生み出されるブドウから出来上がる高品質なワインは世界中のレストランでもオンリストされ始めています。
ブラック・チョーク

英国ハンプシャー、テストバレーの絶景にあるブラック・チョーク・エステートは、自社の醸造所で丹精込めて造られたスパークリングワインやスティルワインを味わうことができます。こちらのワインは美しく洗練された味わいを表現していますが、イギリスでワインを造ることは、挑戦に満ちた冒険であるという現実を常に忘れず、真摯に向き合うことを理念としています。
2015年、CEO兼ワインメーカーのジェイコブは地元ハンプシャーのブドウ畑からブドウを購入し、新たな挑戦を始めました。彼の目標は、英国のワイン業界に新風を吹き込むことでした。既成概念にとらわれず、ハンプシャー産ブドウの特徴である鮮やかさ、純粋さ、精密さ、新鮮さを最大限に引き出し、最高品質のスパークリングワインを生み出すことを目指しています。
ハンプシャー州に新しい拠点として壮麗な12ヘクタールのブドウ畑とワイナリーを構え、2020年、自社畑で丹精込めて栽培した最高級のブドウを厳選し、細部にまでこだわり抜いた新作スパークリングワインをリリースしました。
日本ワインの今:二つの顔を持つ島
日本の伝統産地では
日本の代表的なワイン産地である山梨県甲府市は、過去100年間で平均気温が約2℃も上昇しました。その影響で、ブドウの色づきが悪くなる「着色不良(赤熟れ)」やブドウの成長が止まってしまう品種も出てきています。特に山梨ではカベルネ・ソーヴィニヨンで発生しており、違う品種に植え変える生産者が増えているなど影響があります。このように今まで栽培に適していたブドウが栽培に向かなくなるなど影響が出ています。
北海道の躍進
同じ日本でも北海道を見てみましょう。かつては寒さに強い品種しか栽培できませんでしたが、今ではピノ・ノワールやシャルドネといったフランスの品種が元気に育つようになりました。特に余市町は、雨や雪が少なく、三方を山に囲まれた地形がブドウ栽培にぴったりです!
信濃屋でも北海道のワインを色々取り揃えております。是非、ご覧ください!
おすすめの北海道ワイン

余香ワイナリー『新しく余市町に誕生した家族経営の小さなワイナリー』
昔書いたワイナリーのスタートアップに関する修士論文が忘れられず、家族3人で福岡から北海道へ移住し、新たな挑戦を決意。2018年、北海道余市町登モンガク地区の小高い丘陵地にある耕作放棄地を取得しました。「木村農園のように高品質なブドウを育て、ブルースさんのように高品質なワインを造りたい」 という思いで、ワイン造りへの第一歩を踏み出しました。30年以上放棄されていた農地の開墾には多くの苦労があり、何度も現れる巨大な石や硬い岩盤と格闘しながら、4年かけてようやく植栽が一段落。ブドウの樹が小さな実をつけ、まとまった収量を確保できるようになった頃、醸造所を建設しました。

naritaya (ナリタヤ)『蕎麦と日本ワインの二刀流 』
2020年の春に自社畑に植えた約800本の3年目のブドウから今年は904本のワインができました。2022年は2021年に比べると雨も多く病気が心配されましたが、幸い影響は最小限で10月14 日、晴天の中、合わせて999.4kg のシャルドネ、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、リースリングを収穫することができました。今回も、同じ仁木町旭台にあるル・レーヴ・ワイナリーさんに委託醸造を引き受けていただき、たくさんの方に助けていただきながらnaritayaの2022年度ワインが生まれました。

千歳ワイナリー『山梨県の中央葡萄酒により誕生した北の産地に特化したワイナリー』
千歳ワイナリーは1988年、山梨県勝沼町(現・甲州市)にある中央葡萄酒株式会社の第2支店グレイスワイン千歳ワイナリーとして北海道千歳市に創業。世界水準の国産・自社製ピノ・ノワールの醸造を目指し北の銘醸地に醸造拠点を設けました。その後、2011年にグレイスワインより分社独立。北海道中央葡萄酒株式会社「千歳ワイナリー」として、北の産地に特化したワインの品質を高める努力を重ねています。
私たちの楽しみ方:ヴィンテージの物語
一般的に言われている「良年」といえば、暖かくてブドウがよく熟した年でした。
しかし、冷涼でブドウがゆっくりと育った年は、その年ならではの繊細が光り、美しい酸味、透明感など「良年」では決して味わえない面白さがあり、このようなヴィンテージを好む方も増えてきています。
ワインのラベルに書かれた「ヴィンテージ(年)」は、もはや単なる製造年ではありません。その年のワインストーリーを私たちに語りかけてくれます。
おわりに:進化するワインに乾杯を!
気候の変化はワインにとって試練でもありますが、それ以上に新しい可能性の扉を開いてくれています。伝統あるフランスやイタリアなどのワインも、これまで以上に多彩な表情を見せてくれるでしょうし、北海道や英国といった新しい産地の挑戦にもワクワクさせられます。
だからこそ、次にワインを飲むときはちょっと想像してみてください。
「この1本は、どんな気候と、どんな生産者の工夫から生まれたんだろう?」
そう思いながらグラスを傾ければ、きっとワインがもっと愛おしくなるはずです。
さあ、未来へと進化するワインに、今日も乾杯しましょう!